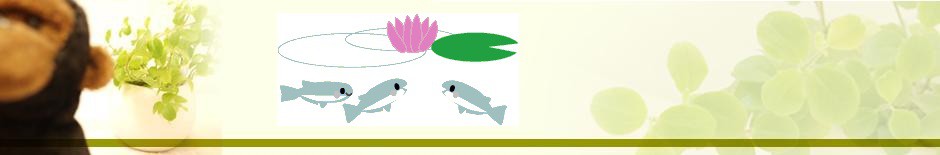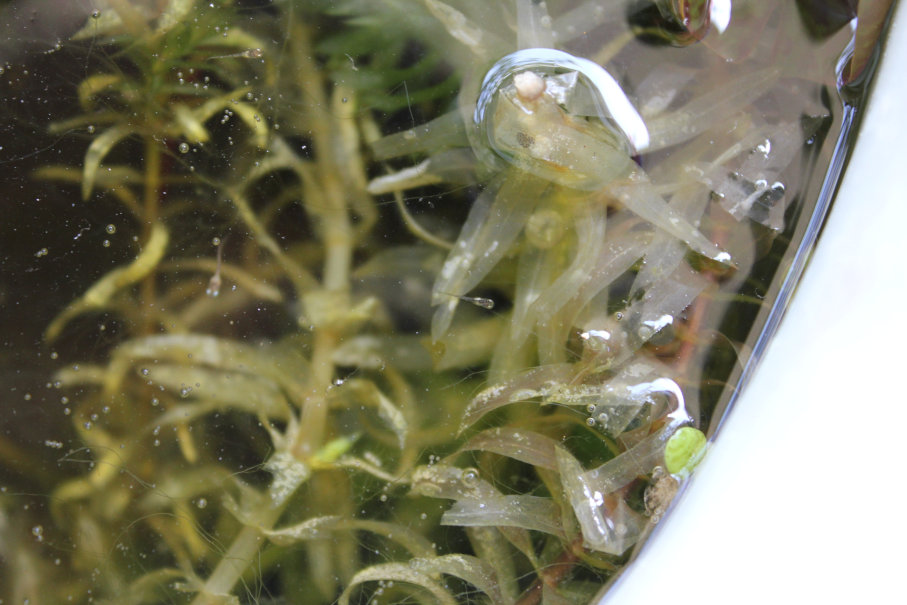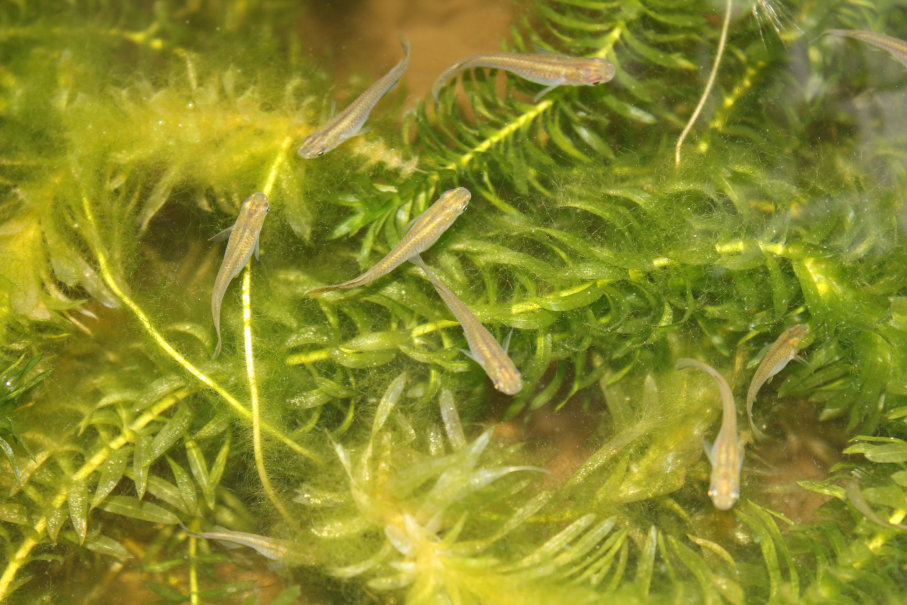梅雨で涼しい日が続きますが、バケツをひっくり返したような豪雨が降る日もあります。
ベランダのビオトープにも水が入り込んで溢れないか心配な日々です。
稚魚睡蓮鉢でも個体差が出てきたメダカの稚魚。
大きい方が楊貴妃メダカ、ちびが黒メダカです。
訳あってまだ小さいかと思いましたが、楊貴妃メダカの稚魚を成魚と同じプランターに移しました。
幸い普通に食べられることもなくやっています。
そうした理由は、今年はクロメダカの稚魚がまったく大きくならないからです。
生まれていない訳ではありません。
過去の写真を見てみても、クロメダカの稚魚も何匹か生まれています。
でも、針子より大きくなりません。
いくつか仮説がありますが、楊貴妃メダカの方が成長が早く強いのかもしれません。
どうした?クロメダカたち。
目が赤い個体もいますね。
ホテイ草がないからあまり産卵しないのでしょうか?
でも、同じ条件でも楊貴妃メダカは産卵しています。
藻にくっついた卵を取っていますが、採る前に食べてしまっている?
もう一つの可能性は数が多すぎることでしょうか?
睡蓮鉢の中には30匹ほどのクロメダカがいます。過密飼育というほどではないと思うのですが・・・。
一番、可能性があるとすれば、新しい血が入っていないこと。
我が家のクロメダカはすべて天然採集ものです。
最初は埼玉県の某水田地帯の用水路から採ってきたメダカたち。
この水田は2000年ごろに行ってたときはすごかったです。
メダカだけでなく、小鮒やドジョウ、アメリカザリガニなども採れました。
魚影が濃く、1000匹単位の巨大な群れがいっせいに泳ぐ姿も見られましたが、そのせいかトリコ(販売目的での採集)も多くいたような気がします。
そして、静岡県の某市の水田地帯の用水路。
埼玉県ほどではありませんが、ここも比較的容易にメダカを掬うことができました。
夏になるとイベントとして、メダカの採集に行っていたのですが、最近は行っていません。
あまり採れなくなり、ボウズの日も出てきたからです。確実に自然は破壊されていっているのですね・・・。
それ以降、限られた中で交配が続いているので、血が濃くなっているのかもしれません。
奇形のようなメダカは生まれていませんが、あまり成長しないのはその辺に理由があるのかも?
とりあえず、今年の残りのシーズンはクロメダカを中心に採卵していきたいと思います。
せめて一匹でも大きくなって欲しい。
そして、できれば自然採集にも行ってみたいですね。